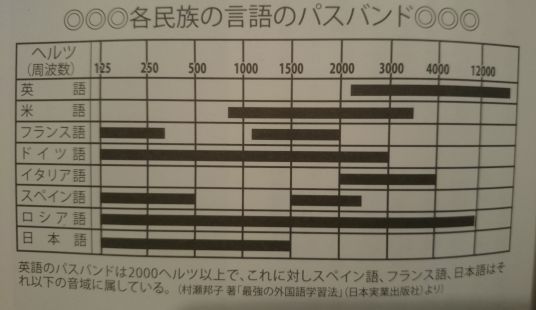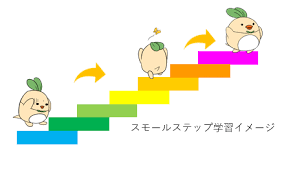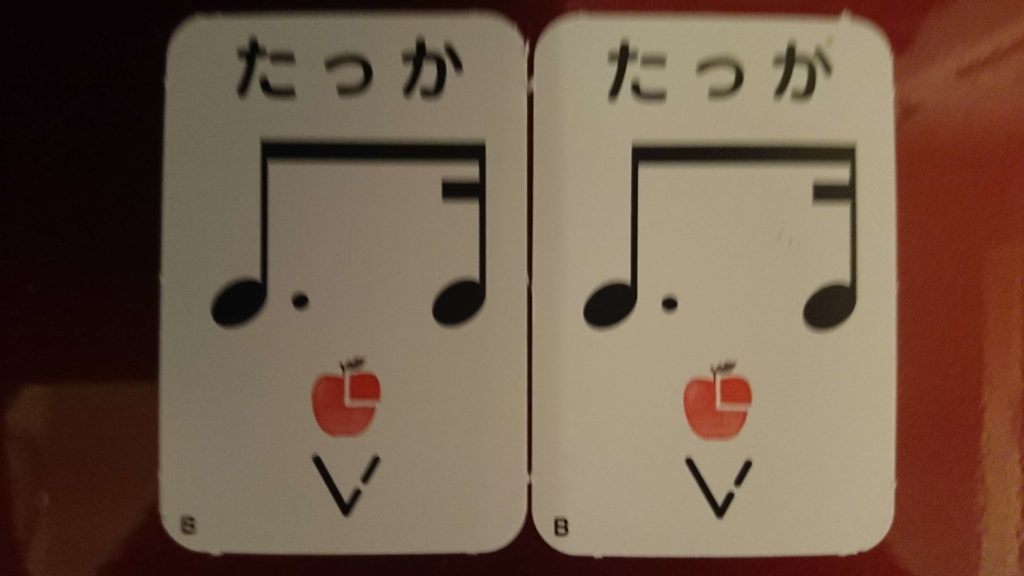あなたは、聴くということから
どんな影響を受けていますか?
または、受けていること事体、
自覚されておられないでしょうか?
まず、なぜ聴くと云うことをここで、
お伝えしたいかという理由を考えてみますね。
あなたも、私も、現実世界、環境と
自分の持つ世界観とを、5感を基軸にして捉えています。
ですから、5感を鍛え、磨いていくと、
現実世界の見えかたを変えることができます。
聴覚について
人の持つ5間のなかでも、「聴覚」は、
最も速い時点で、発達します。
「聴覚」は、受胎18周前後から機能し始め
24周で積極的に聴くようになります。
おなかの中の刺激は、音が一番変化があり、
胎児であった、あなたのお子様も
音で毎日学習していました。
ママの胎内音を聴いて、お子様は育たれたのです。
赤ちゃんの時には、15ヘルツ~2万ヘルツまでの
音域の音を完全に聞き取る能力を持っています。
その後、赤ちゃんが育つ環境にない音、
馴染みのない音は、取り入れなくなり、
日本に生まれた赤ちゃんは
日本語「150ヘルツ~1500ヘルツ」の
低周波領域のみしか聞き取れなくなっていきます。
音の周波数について【音楽&言語】
下記の表はそれぞれの言語の持つ周波数の領域を
示しています。
一度言語を聞き取る周波数領域が固まってしまうと、
よほど、専門的なメソードを実践しない限り
はなかなか、他言語の周波数帯の音を認識できません。
音楽もことばと同じです。
どちらも音の周波数という点で同じです。
以前、日本人の耳の周波数で聴くモーツァルトの交響曲と
イギリス人の耳の周波数で聴くモーツァルトの曲を
ききくらべたことがあります。
日本人によるものは、音色がもの哀しくこもった響きでしたが、
イギリスのものは、キンキンしたきらびやかな音色だったことを
思い出しました。
二つの演奏自体の周波数が異なった結果なのでしょう!
とても、興味深かったです。
【音声には耳で、聞き取れる音しか出せない】トマティス効果
ここで、大切な法則をお伝えしますね🎵
音声には耳が聞いたもの以外は、含まれない❗
咽頭は耳が聴くことのできる倍音しか発しない❗
この法則があるので、音楽表現や、演奏に
国の影響があります。
各国の言語には、特有な周波数領域の音声があり
その言語にない周波数域の音は音楽表現や演奏に
出せないのです!
それで、音楽の表現にその国の言語の影響がでて、
それぞれの、演奏する音楽の音質が変わってしまうのです。
また、あなたの住む地域の地形や環境の影響で、
同じ言葉や音でも、違う周波数の響きになります。
小さな島のイギリスからアメリカ大陸に移ったために、
口先を使う英語と鼻音の多い米語は、相当異なる言語になりました。
日本語も、地域により通じないほどの変化があります。
ここまでで、あなたが、
お子様にどのような音環境を整えてあげるかの
大切さが理解していただけたかと思います。
ここからは、どのような音環境を整えれるのか。
何をどのように聴くかを、探っていきましょう!
周波数の高い音に触れる
言語について語った際、周波数
についての表を見ました。
日本人の周波数帯は低めですから、周波数の高めのものを
選んでおうちでお子様と聴くようにしましょう!
周波数の高い音は脳内のエネルギーを、チャージしてくれる働きもあるので、
どんよりしてしまうときなど、役立てれるでしょう!
また、あなたが聴く時には、
「気導音 と 骨導音」の2つの経路から
聴いていることも理解しておく必要もあります。
それがよくわかるのは自分の声を録音したときです。
自分の骨に響く骨導で聞く音と、自分の声が気導音として
の音が全然違うのです。
ハミングを行うと骨導音のことがよく理解できます。
また、イヤホンだけで聞くにではなく、生演奏を聞くほうが
骨に響くのでインパクトが大きく心地よく感じますし、
オーディオ音は、2万ヘルツ超の音をカットしていて、
高音の音色、つまり倍音が、生だと輝くばかりに聞こえてきます。
私が生徒とよく行うものですが、ピアノの一音を、
ズーッと、ならします。
すると、ピアノの音の特徴が消えて、単なる音の響きになります。
その音に、自分のハミングの音を被せて融合させる訓練です。
まとめ
このように、日頃聞くことのない周波数の音や
楽器の音を豊富に聞くことにより
自分の耳が求める音質や周波数域が変わっていき、
自分の演奏がとても、美しい響きを帯びてくるのです。
あなたがお子様に話す声、お子さまの演奏の響きを
素敵なものにするため、
今すぐ、周波数の高い、あるいは広い音楽をバックミュージックとして
活用してまいりましょう。
ご紹介できる曲としては、断然、モーツアルトの曲です。
これについては説明が長くなるので、のちに記事を書きますね。
ほかに、ユーミンの曲や、坂本龍一氏の【エナジー】などを、挙げられます。
最後までお読みくださりありがとうございました。